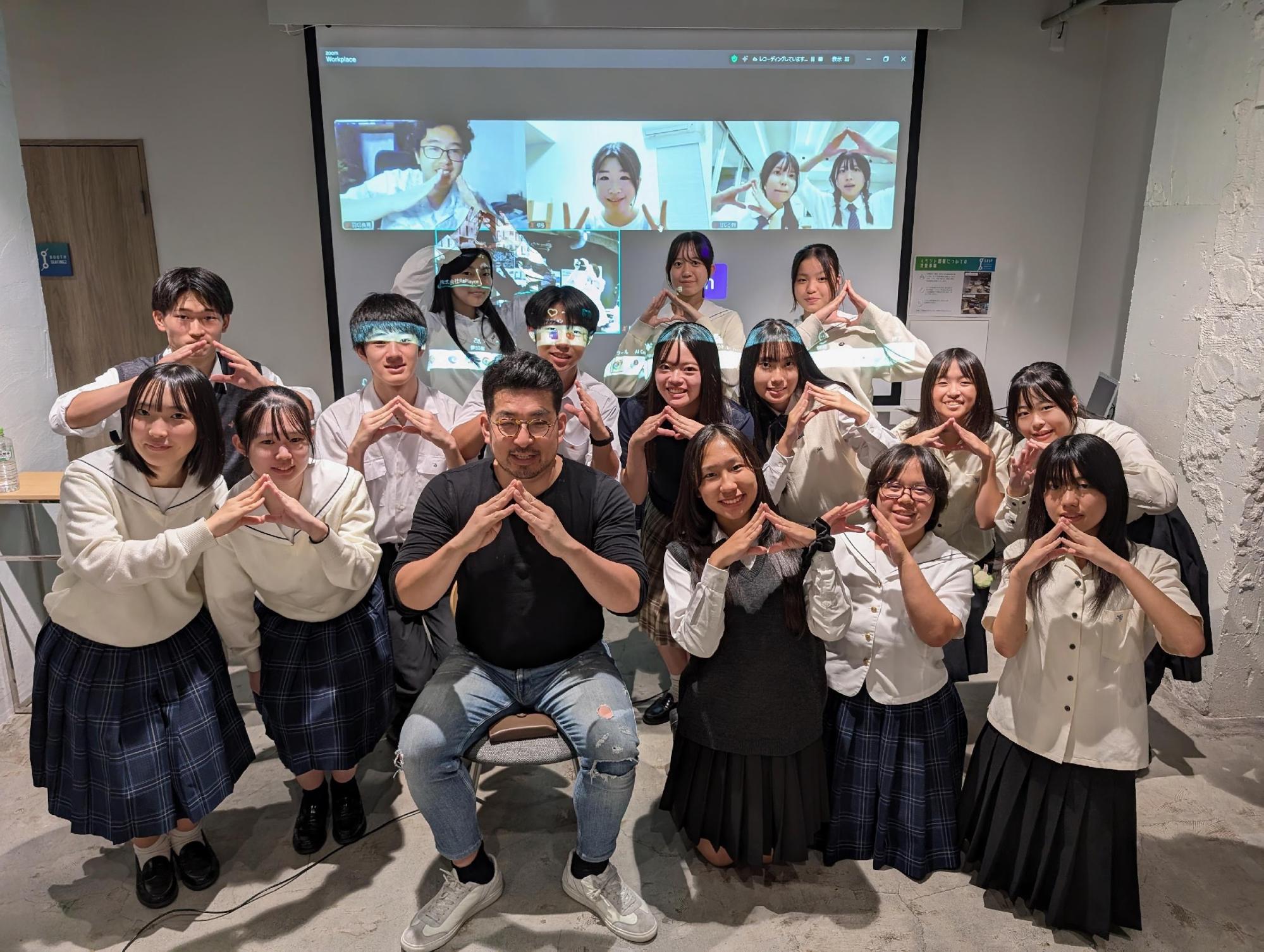10月2日、FuJIプログラム第2期の講義がSHIPで開かれました。第3回となるスキル講義のテーマは「ユーザーインタビューの極意」。講師を務めたのは、スタートアップ支援の第一人者であり、「起業家の参謀」として知られる株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO・田所雅之氏です。
講義冒頭では、田所氏のリクエストで1期生4名が登壇し、2期生に挨拶。田所氏は、第1期でも講師を務め、成果報告会では審査員として彼らの成長を目にしました。田所氏はそのときのことを「感動して泣きそうになった」と振り返り、「高校生の挑戦こそ未来を変える」とエールを送りました。
講師紹介
田所 雅之 氏
株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO / 関西学院大学経営戦略研究科 客員教授

これまで日本で4社、シリコンバレーで1社起業をした連続起業家。2017年発売以降115週連続でAmazon経営書売上1位になった『起業の科学 スタートアップサイエンス』及び『御社の新規事業はなぜ失敗するのか? 企業発イノベーションの科学』『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』の著者。2014年から2017年までシリコンバレーのVCのパートナーとしてグローバルの投資を行う。現在は、スタートアップ経営や大企業のイノベーションを支援するユニコーンファームのCEO及びブルーマーリンパートナーズの社外取締役を務める。年間の講演回数は160回(2019年実績)、新規事業アドバイス/メンタリングは600回(2019年実績)。内閣府タスクフォース(価値デザイン社会審議会)メンバー、経産省主催STS(シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援)の協議会メンバー、経産省主催TCP(ベンチャー支援プログラム)のメンター/審査員などを歴任。
新規事業を成功させる「ゼロイチ思考」
田所氏は、多くの人が当たり前のように使っているスマートフォンやYouTube、Zoomといった便利なサービスが、すべて「ゼロからの発想(ゼロイチ)」によって生まれたことを強調しました。
「10代のうちにゼロイチを経験することは、将来の財産になる」と語りかけ、若いうちに挑戦することの大切さを伝えました。
その言葉を裏付けるように、若くして世界を変えた起業家たちの例を紹介しました。
「YouTubeが生まれたのは(創業者が)25歳のとき、Instagramは23歳のとき。高校生の皆さんとほとんど年齢が変わらない若者が、世界を変えるサービスを生み出した」と語り、高校生のうちにゼロイチを経験する意義を、実例を交えて伝えました。

「学習にフォーカスする」姿勢が成功のカギ
田所氏は、新しい事業を成功させるために最も重要なのは、学びにフォーカスする姿勢だと強調しました。多くの起業家がつまずくのは、「思い込み」や「ひらめき」だけを頼りに事業を進めてしまうことにあると指摘します。
いまやAIを使うのが当たり前の時代となり、ビジネスでも生成AIが活用されています。一見、AIが新しい価値を生み出すかのように思えますが、田所氏は「AIを使いこなすこと」と「新しい価値を生み出すこと」は別の話だと語りました。
「ChatGPTのような生成AIは過去のデータをもとに推論することは得意ですが、今までにない発想を生み出すのは不得手です。新しい価値を生み出すには、現場で試し、失敗から学ぶことが欠かせない」と語りました。
「差別化」より大切なこと。顧客ニーズをとらえる力を磨こう
講義中、2期生から「競合とどう差別化すればよいか」という質問が出ると、田所氏は「差別化だけでは足りない」と即答しました。
「差別化」は競合を基準に考える発想であり、その結果、顧客のニーズからずれてしまうことが多いといいます。
本当に価値ある事業を生み出すには、「顧客のニーズ」「自分たちが提供できること」「競合が提供できていないこと」を意識することが大切です。田所氏は、この三つが重なる部分にあるUVP(Unique Value Proposition)を見つけることが重要だと説明しました。
UVPの考え方を体現する例として、田所氏はユニクロの現場主義を紹介しました。ユニクロが現場を重視し、顧客のミリ単位の変化を捉え続けている姿勢を紹介。柳井正氏が売り場で陳列やサイズ展開を細かく確認し、その気づきからヒートテックやエアリズムといったヒット商品が生まれたことでも知られています。

ユーザーインタビューには「罠」がある
顧客の声をどう聞くかに続き、田所氏は「どう掘り下げるか」という観点からユーザーインタビューを紹介しました。田所氏は「顧客の声を聞くことは大切だが、そこには多くの罠がある」と警鐘を鳴らし、具体的に2つの罠を紹介しました。
ひとつ目の罠は、相手がつい口にしてしまう優しい嘘。特に高校生など熱意ある若者に対して、大人は「いいね」「頑張ってね」とポジティブな言葉を返しがちで、それが本当の需要の有無を見誤らせる原因になると指摘しました。
もうひとつは、「アホに見られたくない問題」です。インタビューを受ける側が「できない」「わからない」と言いたくない気持ちから、本音を隠してしまう現象です。「特に高校生が大人にインタビューすると、『だらしない大人と思われたくない』という心理が働き、本音を話してもらえないことがある」と田所氏は話します。
解決策として、田所氏は「相手をリラックスさせ、『普通の社会人として正直に教えてください』と伝えるだけで、本音を引き出しやすくなる」とアドバイスしました。
顧客の「隠れた不満」を見つける、モチベーショングラフ
田所氏は、顧客の言葉にならない本音(インサイト)を探る手法として「モチベーショングラフ」を紹介しました。ある体験を時間の流れに沿って振り返り、その時々の感情の高まりや落ち込みを線で描くことで、「人が不満を抱いて諦めている瞬間」を見つけ出す手法です。
田所氏は「人は諦めている部分にこそ新しい価値のヒントがある」と語り、 潰しやすいペットボトルや 「ニトリのスマホ毛布」など、身近な不便を解決した事例を紹介しました。
後半のワークでは、生徒たちが自分の生活を題材にモチベーショングラフを作成。「旅行の待ち時間」「家族との意見のすれ違い」「お祭りの混雑」など、日常の不便を洗い出していきました。田所氏は「身近な課題の中にこそ、新しい発想のヒントがある」とまとめました。

まとめ
今回の講義では、顧客理解の重要性と、相手の本音を引き出すコミュニケーション法を学びました。
田所氏は「成功する起業家ほど学び続ける姿勢を大切にしている」と語り、「自転車と同じで、転びながら学ぶもの」と高校生たちを励ましました。
講義を終えた2期生からは、「差別化よりも、顧客と自分たちの価値が重なる部分を見極めたい」「モチベーショングラフで日常の不便を見える化できた」「顧客に正直に答えてもらう前置きが大事」といった感想が挙がりました。また、「観光客を観察して課題を探す」「高校生ではなく一起業家として挑みたい」と、次の行動につなげようとする前向きな声も聞かれました。