8月中旬に始まった第2期のFuJIプログラム。3泊4日のスタートアップキャンプでは、2期生たちが出会い、多くの学びを得て次の挑戦へ向けた意欲を高めました。
9月11日には、キャンプ後初めての講義をSHIPで開催。講師はスタートアップエコシステム協会代表理事の藤本あゆみ氏。Googleでの勤務やスタートアップ実務、起業経験など幅広いキャリアを持ち、昨年に続いての登壇です。
テーマは「スタートアップの世界」。スタートアップの基本的な概念に加え、起業家に必要なマインドセットや行動指針について熱く語りました。さらに今回は、急速に進化するAIにも焦点を当て、自動運転タクシーや空飛ぶクルマ、義手の動きを制御するAIなど、未来を感じさせる事例も紹介しました。
講師紹介
藤本あゆみ氏
(一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事 文部科学省アントレプレナーシップ推進大使)

2002年キャリアデザインセンター入社、2007年4月グーグルに転職し、人材業界担当統括部長を歴任。「Women Will Project」のパートナー担当を経て、同社退社後2016年5月、一般社団法人at Will Workを設立。その後株式会社お金のデザインを経てPlug and Play Japan株式会社にてマーケティング/PRを統括。2022年3月に一般社団法人スタートアップエコシステム協会を設立、代表理事に就任。米国ミネルバ認定講師。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使、内閣府規制改革推進会議スタートアップ・投資ワーキンググループ専門委員。
マインド講義「スタートアップの世界」での学び

大学卒業後は求人広告の会社に就職し、人材業界の経験を積みました。2007年にGoogleへ転職し、検索や広告の普及に携わる中で、YouTubeが急成長していく様子を目の当たりにし、「未来を変える価値を生み出したい」という思いを強めました。
その後は資産運用サービス「THEO(テオ)」を展開するお金のデザインに参画し、限られた環境の中で仲間と挑戦を乗り越えた経験が大きな糧になったと語ります。現在はスタートアップエコシステム協会の代表理事として、成長支援や教育の推進に取り組んでいます。
実は、藤本氏は中学・高校時代に放送部に所属し、番組制作への興味を深めていました。現在のキャリアとは一見違う道に進んだようですが、「やりたいことを持つ大切さ」と「変化に柔軟であること」を学んだ経験が、今の活動にも通じていると話しました。さらに「進む道は一つではなく、どんな選択をしてもいい」というメッセージを伝え、2期生たちに未来を自由に描いてほしいと呼びかけました。
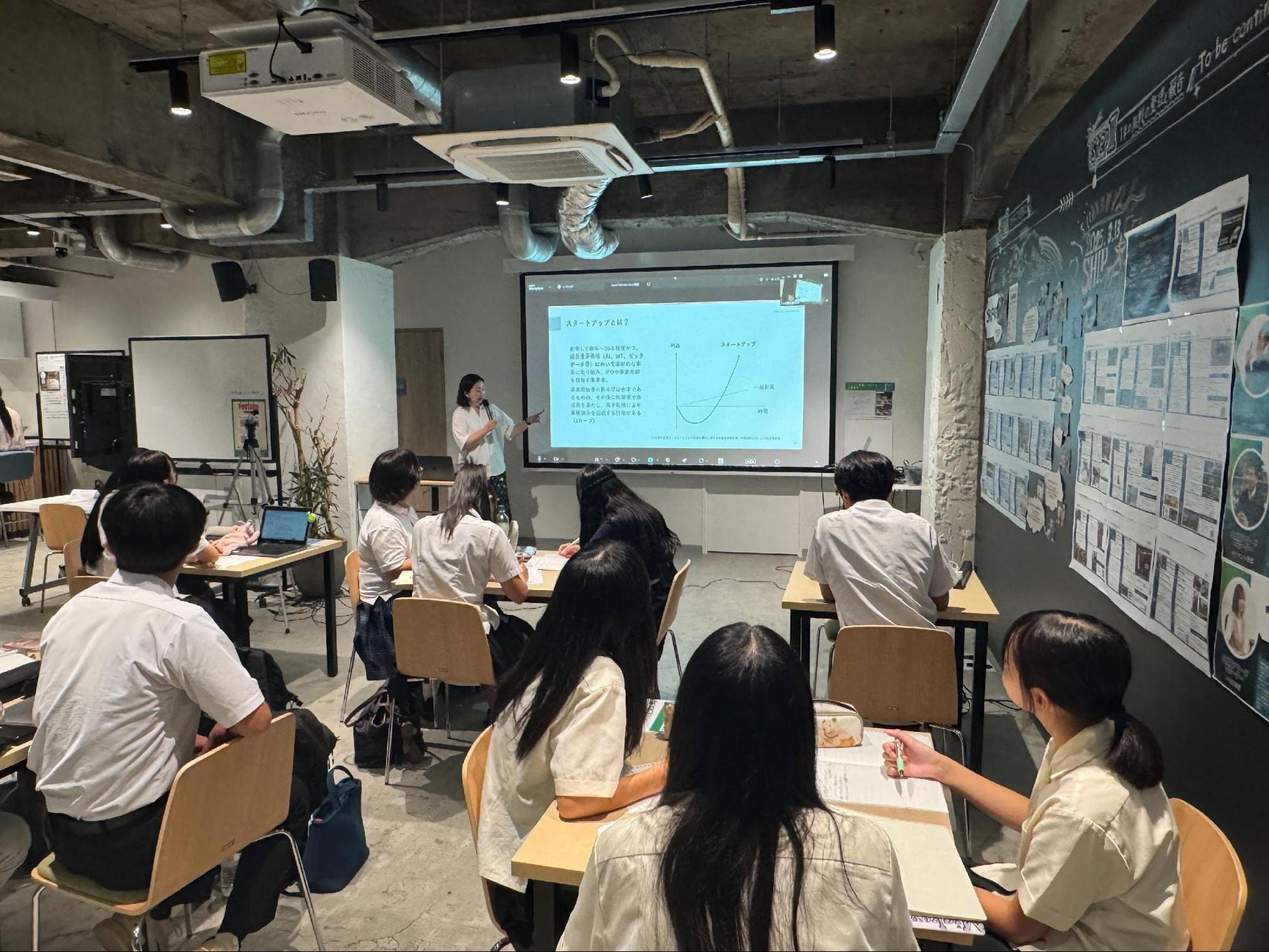
成長の早さは重要
藤本氏は「スタートアップとは未来をつくる存在だ」と強調しました。急成長を目指すJカーブ型だけでなく、地域課題の解決を目指すもの、国内市場を中心に展開するもの、自己資金で成長を続けるものなど、さまざまな形があり、それぞれが社会に必要な役割を果たしていると説明しました。
また、アメリカのスタートアップ育成機関「Yコンビネーター」(Y Combinator)の創設者ポール・グレアム氏の言葉を引用し、「速く成長すること」の重要性を紹介。さらにModernaによるワクチン開発を例に、物事を進めるスピードの価値を示しました。
being(ビーイング)とdoing(ドゥーイング)
存在意義や価値観を指す「ビーイング」と、それを実現する手段である「ドゥーイング」の両方が大切だと説明。ビーイングはぶれない軸とし、ドゥーイングは柔軟に変えることが重要です。そのためのヒントとして、普段どうしても選んでしまう自分の選択を深く考えることや、一駅先で降りてみるなどいつもと違う選択をする小さな挑戦を勧めました。
まず、やってみる。行動が大切
藤本氏は「まずはやってみよう」と呼びかけました。YouTube創業者の言葉を引用し、「子どもが泳ぎを覚えたいなら、まずプールに入れてみる」という例を紹介。挑戦する勇気の大切さを強調しました。「どれだけ準備をしても、実際に水に入ってみなければ泳げるかどうかはわかりません。だからこそ、思い切って入ってみようというシンプルな話です」と語りました。
スタートアップへの関わり方とAI
スタートアップへの関わり方は、創業者になるだけではありません。従業員として働く、インターンとして参加する、支援者として関わるなど、さまざまな形があります。藤本氏は、チームで挑戦を支える役割の重要性を強調しました。
また、AI翻訳の進化によって言語の壁が低くなりつつある今こそ、「シンクグローバル(世界規模で考える)」という視点が欠かせないと指摘。自分に合った関わり方で未来を共につくる大切さを、高校生たちに伝えました。
質疑応答
質疑応答の時間には、2期生から次々と手が挙がり、オンラインで参加者からもたくさんの質問が寄せられました。
Q:海外のスタートアップの情報は、どう調べたらいいですか?
A:クランチベース(Crunchbase)やディールルーム(Dealroom)といった世界中のスタートアップをまとめたサイトがあります。基本的な情報は無料で閲覧できますし、気になる分野を決めて企業を追いかけていくと面白い発見ができますよ。
Q:日本の高校生に足りないものは何だと思いますか?
A:自分の意見を言う機会が少ないことですね。海外ではディベートやディスカッションが当たり前に行われています。何が正しいかではなく、自分はどう思うかを言葉で伝える習慣が出来上がっています。日本の高校生も、もっと発言していいんですよ。
Q:チームメンバー間で意見が割れた場合、どうすればいいでしょうか?
A:考えが違うので、時にぶつかるのは自然なことです。最終的に誰が決めるかをはっきりさせておきましょう。そして、意思決定をした人をチーム全員で応援することが大切です。
Q:いつもと違う選択をする際には、どのような心構えがよいでしょうか?
A:プールの話を思い出してください。まず、やってみることです。やらなければ何も起きませんが、やれば必ず何かが起きて、次へのヒントになります。怖くても一歩踏み出すことが大切です。

まとめ
この日は首都圏で悪天候が重なり、新幹線が遅延。藤本氏の到着も予定より遅れましたが、動揺する様子はなく、落ち着いた雰囲気で講義を開始しました。その姿は「予期せぬ出来事にどう向き合うか」という、まさにスタートアップのマインドを行動で示しているようでした。ビジネスの現場では想定外が必ず起きる。その時こそ冷静さと柔軟さが問われるのだと、高校生たちは身をもって感じたのではないでしょうか。
終了後も多くの参加者が藤本氏のもとに集まり、熱心に質問を投げかける姿が見られました。キャンプでの学びに加え、講義やスタッフとの壁打ちを通じて理解を深めた2期生たちは、これからも自分のアイデアを具体化しながら「スタートアップの世界」に踏み出していきます。
次回は10月2日にスキル講義「ユーザーインタビューの極意」を予定しています。引き続き、ぜひ一緒に応援してください。
